「国際生活機能分類(ICF)」でレポートを書く際に参考にしていただければ幸いです。
なお、当内容を転載してレポートを作成することはおやめください。
あくまでも参考資料として閲覧してください。
レポート内容
国際生活機能分類(ICF)の目的は「健康状況」と「健康関連状況」を把握することであり、人の健康のすべての側面とwell-being(良好な状態)のうち健康に関連する構成要素を記述することにあります。
国際生活機能分類(ICF)は、国際障害分類(ICIDH)が改定されたものです。この国際障害分類(ICIDH)は「疾病の帰結(結果)に 関する分類」とされ、問題が生じた状態を見るものであるため、マイナスモデルと呼ばれており、障害によって社会的不利を捉える一方通行のものです。そのため、社会的不利から障害を捉えるような反対の流れはなく、また、障害だけで判断するため、個人や環境による原因が反映されることはありませんでした。
一方、国際生活機能分類(ICF)は「健康の構成要素に関する分類」とされ、プラスモデルと呼ばれています。6つのカテゴリーが一方通行ではなく相互に関連しているほか、新たに導入された背景因子(環境因子・個人因子)によって、障害は人間と環境との相互作用によって発生することが明確化されています。そのため、ある1人の人を多角的に深く見ていくためのツールとして有効です。
国際生活機能分類(ICF)を用いる場合、個人の状態を各分類毎に整理し、どのようにアプローチするかを検討することになりますが、アプローチの方向性は複数出てくる可能性があります。例えば、心身機能・身体機能を向上させることによって活動性が上がり、参加の意欲に繋げていくことを想定する場合もあれば、環境を変えることによって参加の意欲に繋げていく方法も想定することができます。いずれにしても、国際生活機能分類(ICF)に落とし込むことによって、問題点が浮き彫りになり、アプローチ方法を考えやすくなることが期待されます。
また、アプローチ方法の検討だけではなく、疾病と生活機能を互いに関連させて総合的に把握することで、対象者個人に関する総合的な情報がもれなく医療・保健・介護・福祉・労働・教育等の異なったサービス分野の間で(また同じ分野の中でも)共有することが可能となり、対象者個人の情報を正確かつ効率的に伝達されることが可能となります。

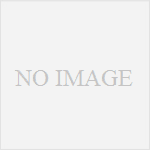
コメント